【toiro】苦手なことにもちょっと取り組む効能について
私たちはどうやら、得意なことよりも、苦手なことを自覚しやすくできているようです。
考えてみればこれも自然なことなのかもしれません。得意なことは本人にとっては「当たり前」のことですから(魚はきっと、えら呼吸ができることを不思議に思ったりはしないでしょう)。
一方で苦手なことは目につきます。一生懸命取り組むわけですが、当然ながらなかなか上達しません(何しろ苦手なわけですからね)。できることが増えたとして、得意な人と同じようにできるかというとそうでもない。がっかりされた経験がおありのかたも、きっといらっしゃるのではないのでしょうか。
では、苦手なことは全部やらなくてもいいんでしょうか?
今日もさっくり結論から行きます。
「自分が考えて、行動して、目的を達成したという経験」あるいは「どれくらいできないかを正しく知る経験」そのもののために、苦手なこともちょっとやってみる意味はある、と。
私たちの考える自分自身が「明確に固定されて存在している」のかというと、半分はそのとおりで半分は違っています。
DNAをもとにつくられた体の傾向はそうそう変わらない一方で、生まれてから生きているうちにつくられてきた部分も多々あります。考え方の癖、住んでいる環境、体験したものごとをどう解釈したか……この後半部分は、工夫と振り返り、考え方によって、変えることができる部分です。
もちろん簡単に変わるとは限りません。結局目標には届かないかもしれません。だとしても、自分のできること、あるいはできないことを正しく知るために、その経験は役立ったと言えるはずです。
現在の私たちの暮らしにおいては、あらゆることが望み通り、というわけにはいきません。けれども望み通りにできることもあります。自分が決めて工夫して、望み通りにできることは確かにあると身をもって学ぶために、苦手なことにもちょっと取り組んでみてもいいと思うのですよ。あとはもちろん、自分自身の自由のためにも。

+++++++++++++++++++
コラムtoiroは、発達障がいやコミュニケーションに苦手さを感じているご本人、学生さん、お子さんを応援するコラム。名前は、十人十色からつけました。
読者の方にとって、少しでも役に立つヒントになればうれしく思っています。
不定期ですが、ちょっとずつ更新していきます。
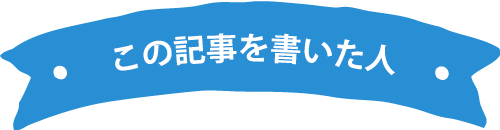
発達障がい当事者。お仕事では記事の執筆・イラストの制作・動画制作などを行っています。
ピアサポートグループの活動・講演会への参加などを通して、地方の町から発達障がいに関する発信を行っています。
こちらのブログ「toiro」では、自分自身の体験・身近な方々の体験談に基づいて「日常生活での気づき」「実際に役立った、二次障がいへの対処・予防方法」「猫の観察記録から学んだ、発達障がいとのつきあい方」などの記事を作成しています。






