【toiro】スポーツを楽しむ、選手以外の方法
みなさんはスポーツはお好きでしょうか? こう訊ねたら、渋い顔をなさる方もいらっしゃるかもしれませんね。
かくいう私も小中学校を通して、チームでのスポーツは大の苦手でした。発達障害の人にときどき見られる「体を動かすこと自体が苦手」という特徴に加え「チームメイトにうまく説明ができない」というコミュニケーション問題。卒業時には、もう二度とこんなことはしないぞ、と心に決めるくらいでした。
大人になればもちろん、無理にスポーツを好きになる必要はありません。ただ、ちょっとでも楽しめれば活動の場が増えることも事実。というわけで、スポーツにどう関わっていけばいいのか、提案をしてみたいと思います。
試すことはこの2つです……「選手として活動するほかにも、役立てる活動を探すこと」「自分のできる範囲で、役立てる活動を楽しんでみること」
プロのスポーツの世界を見ていると、わかりやすい役割もある一方で、なかなか目につかないながら必要不可欠な役割もいくつもあります。
たとえば野球であれば、試合に出る選手のほかにも、一緒に働いている人はたくさんいます。監督やコーチはもちろん、データ分析担当、球団の企画運営に広報、審判に栄養士。用具やグッズのメーカーにまで目を向ければ、野球というスポーツに貢献している人は私たちの想像以上にいらっしゃいます。
趣味や部活動でのスポーツであっても、選手のほかに多くの役割があるのは同じです。むしろ選手よりも、求められる力の種類は多岐に渡るように思われます。その中には、私たちに役立てることもあるかもしれません。少なくとも、そのスポーツ自体が好きなら、できることはたくさんありそうです(それこそ「二度と関わらないぞ」なんて言う前に)
チームでのスポーツは、遊びのひとつとして、私たちが小さい子どものうちに始めて経験することが多いものです。
自分の得意なことも苦手なことも、コミュニケーション技術も未熟なうちの経験です。問題をかかえて、スポーツ自体が嫌になってしまうこともきっとあることでしょう。
でも、自分が成長してから「やっぱりスポーツを楽しみたいな」と考えると、選手になる・自分が活躍するほかにも、楽しむ方法はたくさんあるようです。
皆さんも、よかったら試してみてくださいね。

+++++++++++++++++++
コラムtoiroは、発達障がいやコミュニケーションに苦手さを感じているご本人、学生さん、お子さんを応援するコラム。名前は、十人十色からつけました。
読者の方にとって、少しでも役に立つヒントになればうれしく思っています。
不定期ですが、ちょっとずつ更新していきます。
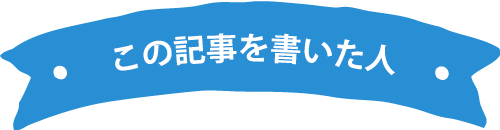
発達障がい当事者。お仕事では記事の執筆・イラストの制作・動画制作などを行っています。
ピアサポートグループの活動・講演会への参加などを通して、地方の町から発達障がいに関する発信を行っています。
こちらのブログ「toiro」では、自分自身の体験・身近な方々の体験談に基づいて「日常生活での気づき」「実際に役立った、二次障がいへの対処・予防方法」「猫の観察記録から学んだ、発達障がいとのつきあい方」などの記事を作成しています。






